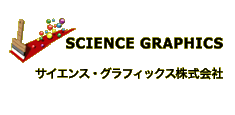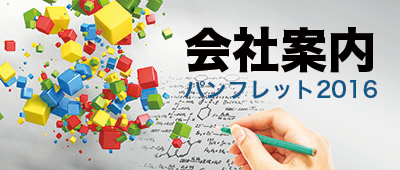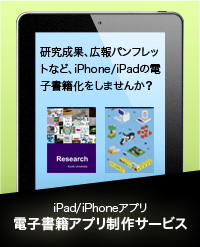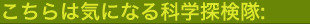先祖は遠く宇宙から…
この記事では、 という内容を取り扱っています。 宇宙空間で生命がはじまった?1月30日に”Proceedings of the National Academy of Sciences”という科学誌にこの記事が載ってからというもの、そのニュースは世界中を瞬く間に駆け巡りました。 その内容を簡単に紹介しますとこんな感じです。 宇宙空間での反応をシュミレートするために、ごく低温の状況下で、宇宙に多く存在するアンモニアや一酸化炭素、二酸化炭素といった小さな分子に紫外線を照射し、その結果、原始の細胞膜に似た膜が生成されたというのです。 では、これのどこが驚きなのでしょうか。実は、この実験により、生命は宇宙空間からはじまったという信頼性がより高まったと言えるのです。さらに、今でも生命は宇宙空間のいたるところで存在しているかもしれないということも言えるようになりました。確かに、今までに地球の生命は宇宙からやってきた隕石によってもたらされたといった生命飛来説といものはありました。でも、これは数年前まで、科学者の大多数がバカげた説だと言って、SFの話を持ち込まないでくれといった具合にまじめに議論するようなことはありませんでした。 ところが、今回の発見により、もはやSFで笑い飛ばすわけにはいかなくなったのです。 では、今回のことを詳しく見る上で、まずは何が直接のきっかけになったのかということからはじめてみましょう。そのためには、いったん1998年の、ぎらぎら照りつける太陽の下、ヤシの木がなんとも魅力的に茂る、カルフォル二アのNASAエイムズ研究センターのロウ・アラマンドラの研究室に行ってみる必要があるでしょう。 はじめはカルフォル二アのある研究室で起こったいつものことながら、その研究室では耳をふさぎたくなるほどの騒音が鳴り響いていました。その騒音の原因は何かというと、高出力の冷却装置によるものでした。アラマンドラは、その装置によって、ほぼ絶対零度という宇宙空間そっくりな環境を密封空間の中に作り出していたのです。その密封空間の中には、水蒸気や、メタン、アンモニアといった気体の混合物が含まれていました。他には核となる微小なアルミニウムイオンやセシウムイオンもその中に含まれていました。そして、そのイオンを核として、その周りに気体が付着していくというわけです。こうして付着する分子の数が増えて凝固すると、氷上の白い層となりました。 さらに、紫外線があふれている宇宙空間を再現するために、その粒子に紫外線を照射しました。すると、H2OやNH3などの混合気体分子の化学結合が切れ、反応性の高く、不安定なOHやNH2といった物質にかわりました。しかし、思い出してください。そこは先ほども述べたようにほぼ絶対零度という低温なのです。高温のところでは、分子は大きなエネルギーをもっているので互いの分子間力につかまることなく飛び回っていますが、このような低温下では、すぐに互いの分子間力につかまってしまいます。そして、すぐに近くにある分子とお互いに反応しあってしまうのです。さらに、ここで注目したいのは、普通の温度なら結合する分子というのは、お互いが反応によって安定になるものに限られているのですが、このような低温状況では、分子の運動は不活発で、はじめに近づいた分子の分子間力につかまり、安定か不安定かには関係なく新しい化合物を生成しまうのです。したがって、普通の温度では生成しえないような化合物が生じることがあるのです。 (参考:装置の解説) 言ってしまえば、この実験というのは、料理のわからない子供がレシピ通りつくっているようなもので、何ができるかはわからないというものなのです。つまり結果を予測したり、また生成物を観測することは、非常に困難なのです。そのため、その真空装置には、質量分光装置や赤外線分光装置といったものが取り付けられていました。赤外線スペクトルを観測することによって、生成物の構造をつかんでいたのです。 ところで、今までにNASAの他のチームでは、似たような実験の結果としてアルコール、ケトンなどの小さな有機化合物、それにヘキサメチレンテトラマイン(HMT)といった大きな有機化合物などといったものを確認していました。 しかし、そのときのアマンドラの実験結果は、それらとはまったく異なる別の物質だったのです。しかし、そのときのアマンドラにはその物質が何かまったく見当がつきませんでした。 小空胞の正体をつかめさて、ここで、もう一人のキーパーソンが登場してもらいましょう。カルフォル二アのサンタ・クルツにある大学の生物学者、デビッド・ディーマーです。 ディーマーは以前、1969年にオーストラリアに降ってきたマルチソン隕石について研究していたことがありました。この隕石は、多量の有機物分子を含んでいたということで、当時から科学者の注目を集めていた隕石でした。そして、ディーマーも同じく、その隕石に興味を抱いていたのです。ディーマーは砂岩のようなその隕石から、なにか奇妙なものを発見した。それは非常に微粒な小球体でした。。そこで、ディーマーはその隕石のかけらを粉状にした後に、その有機分子をゆすぎ出すためにその粉末を溶媒に溶かしました。するとでてきたものは、液体の中で漂う二層の小空胞だったのです。しかし、ディーマーがこの発見をを1985年のNATUREに発表したとき、他の科学者はそのことをまじめに取り扱おうとしませんでした。少なくとも当時の科学者にとって、その小空胞が何なのかということはわからなかったのでしょう。ましてや、それがどんな反応によって生成するなどということは知る由もなかったことでしょう。 いずれにせよ、その程度のことで興味を失わなかったディーマーは、先ほどのアマンドラの実験の噂を聞きつけ、そして、その研究室のドアをたたくことになりました。 そこでディーマーが見てみると、まさに過去に自分が見たあの小空胞が頭の中をよぎりました。そこで、ディーマーは、その密封器のなかの残留物を取り出し、水で温め、詳しく観察したところ、それはちょうど赤血球のような大きさ、形をしたものでした。さらに二人が発見したことは、紫外線のなかではその小空胞は蛍光を発するということと、その小空胞が複雑な有機分子から構成されているということでした。 まさに、数年前まではSFと考えられていたことが、起こってしまったのです。そう、水溶性の分子量の小さな物質から、複雑な有機化合物に変化するということが。 細胞との関係はその後、ドワーキンが、その小空胞を詳しく観察するため、その残留物を洗浄したあと、観察に必要な量を得ようとしていました。しかし、それは容易なことではありませんでした。真空を作り上げる装置を連続して何週間も運転しつづけることで、その中には小空胞以外にも別の化合物が多く生じてしまうからです。何とか観察に必要な量を取り出したドワーキンは、それを詳しく観察しました。すると、その化合物は脂質のような振る舞いをすることがわかりました。その脂質というのは、まさに今の細胞膜の主成分と同じものなのです。 その分子は、ちょうど石鹸の分子のように、得られた分子も、一方の端は水をひきつける親水性を示し、もう片方の端は、水になじまない疎水性を示したのです。つまり、この小空胞は細胞膜と同じように、親水性を示す側は外側になり、疎水性を示す側は内側で中の物質を包み込むという働きをするということがわかったのです。 このようなことから、急に生命飛来説というものが注目されるようになったのです。もはや、かつてのSF話が現実味を帯びてきました。
関連サイト
|