■レーザー
−レーザーの原理2:反転分布
 |
| 1960年にT.H.Maimanが発明した固体ルビーレーザーの構造。詳しくは本文参照。 |
レーザーの条件2:反転分布
レーザーに必要な条件とは、前のページで説明したように、コヒーレントな光を可能にする誘導放射だ。ただし誘導放射は自然に起こるものではない。これは次のように説明できる。
誘導放射は、一つ目の再結合が二つ目の再結合の引き金になるというものだった。
ところが、自然な状態での原子や分子の構造について考えてみると、エネルギーの高い軌道にいる電子よりも、低い軌道にいる電子の数のほうが多いはずだ。ということは別の再結合が起こる確率よりも、吸収されて他の電子を励起する確率のほうがはるかに高い。そのため、自然には誘導放射は起こらない。
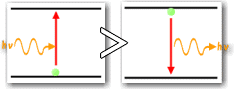
自然な状態、誘導放射が起こる確率よりも他の電子を励起する確率の方が高い。 |
|
そこで誘導放射を起こすためには、高エネルギーと低エネルギーの電子の数の割合が反対でなければならない。つまり、原子や分子全体にエネルギーを与え、高エネルギー軌道の電子の数のほうが低エネルギーの電子の数より多くしてやれば誘導放射がおこる。この状態を「反転分布(population inversion)」と呼んでいる。
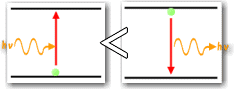
反転分布の状態、誘導放射が起こる確率の方が他の電子を励起する確率よりも高い。 |
|
例えば、世界で最初に発明されたレーザーである「ルビーレーザー」では、ページトップの図に示すように、キセノンフラッシュライトを使って、クロム原子を励起する。これによって高いエネルギーレベルにある電子の数の方が多くなり、反転分布の状態になる。キセノンランプが使われるのは、幅広い周波数成分を含んでおり太陽光に近い白色光なので、ルビーレーザーの赤色光を含んでいるためである。
|
|